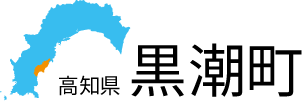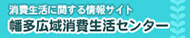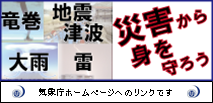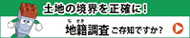児童福祉
児童扶養手当
2025年4月3日 13時31分 更新 2019年2月19日 14時36分 公開

▶▷ 支給対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある児童を監護している父子、母子家庭の父または母や、父母に変わってその児童を養育している方(祖父母等)。
▶▷ 支給要件
以下のいずれかに該当する児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、母または養育者に支給されます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定程度の障害の状態にある児童
・父または母が生死不明の児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
※ただし、次に該当する場合などは、手当は支給されません。
・手当を受けようとしている人、対象児童が日本国内に住所を有さないとき
・児童が児童福祉施設に入所措置されているとき
・児童が里親に委託されているとき
・父または母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき
▶▷ 手当月額 (所得に応じて決定されます)
◆2025年4月~
| 児童1人 | 全部支給:46,690円 一部支給:46,680円~11,010円 |
| 児童2人目以降の加算額 (1人につき) |
全部支給:11,030円 一部支給:11,020円~5,520円 |
※所得が制限を超える場合や、受給している公的年金が児童扶養手当より高額な場合などは手当は支給されません。受給している公的年金が児童扶養手当より低い場合は、その差額が支給されます(平成26年12月より)。
▶▷ 現況届
児童扶養手当の認定を受けている方は、前年の所得状況と、8月1日現在の児童の養育状況などを確認するため「児童扶養手当現況届」の提出が必要です。それにより、11月~翌年10月までの児童扶養手当の額が決定します。
全額支給停止となっている方も、提出が必要です。
※この届出をしないと、当該年度の11月分からの手当の支給を受けられなくなります。
また、提出しないまま2年を経過すると、手当の受給資格はなくなります。
児童扶養手当の現況届の事前送信(電子申請)はこちらをご利用ください。
▶▷ 支給月
下記支給日にそれぞれの前月分までの手当を合計して、ご指定の金融機関口座に振り込みます。
(支払日が、土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日に振込みます。)
| 支給日 | 支給対象月 |
| 1月11日 | 11月~12月分 |
| 3月11日 | 1月~2月分 |
| 5月11日 | 3月~4月分 |
| 7月11日 | 5月~6月分 |
| 9月11日 | 7月~8月分 |
| 11月11日 | 9月~10月分 |
▶▷ 児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、児童扶養手当額が公的年金等の額を上回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
▶▷ 支給制限に関する所得の算定
児童扶養手当制度には、受給資格者と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(受給資格者の父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれます。
(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
| 扶養親族等の数 | 請求者本人 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者 対象所得(※扶養義務者は直系のみ) |
|
| 全部支給対象所得 | 一部支給対象所得 | ||
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
| 加算額 | 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円 |
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 | |
▶▷ 資格の喪失・各種届出について
手当ての支給を受けている方は、認定の請求をしたときと状況が変わった場合には届出する必要があります。・婚姻(事実上の婚姻関係を含む)した場合
・公的年金を受給するようになった場合
・対象児童が結婚した場合
・入所等で監護されなくなった場合
・国内に住所がない場合
・住所、氏名、支払金融機関が変わった場合
・監護、養育している児童の人数が変わった場合
・その他、受給資格に該当しなくなった場合 等
※児童扶養手当の受給資格がなくなったにも関わらず、届出を行わずに手当を受け続けていた場合、その期間の手当金額は、さかのぼってまとめて返納することになりますのでご注意ください。
▶▷ 手続き(申請)について
健康福祉課 福祉係での手続きとなります。
支給要件により必要書類が異なりますので、詳しくは健康福祉課 福祉係までお問い合わせください。
▷▶▷「児童手当」についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
電話:0880-43-2116
電話:0880-55-3112